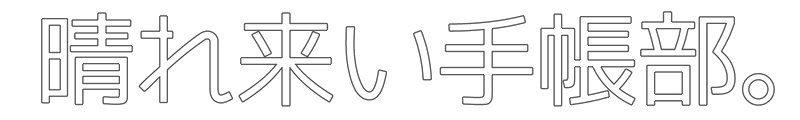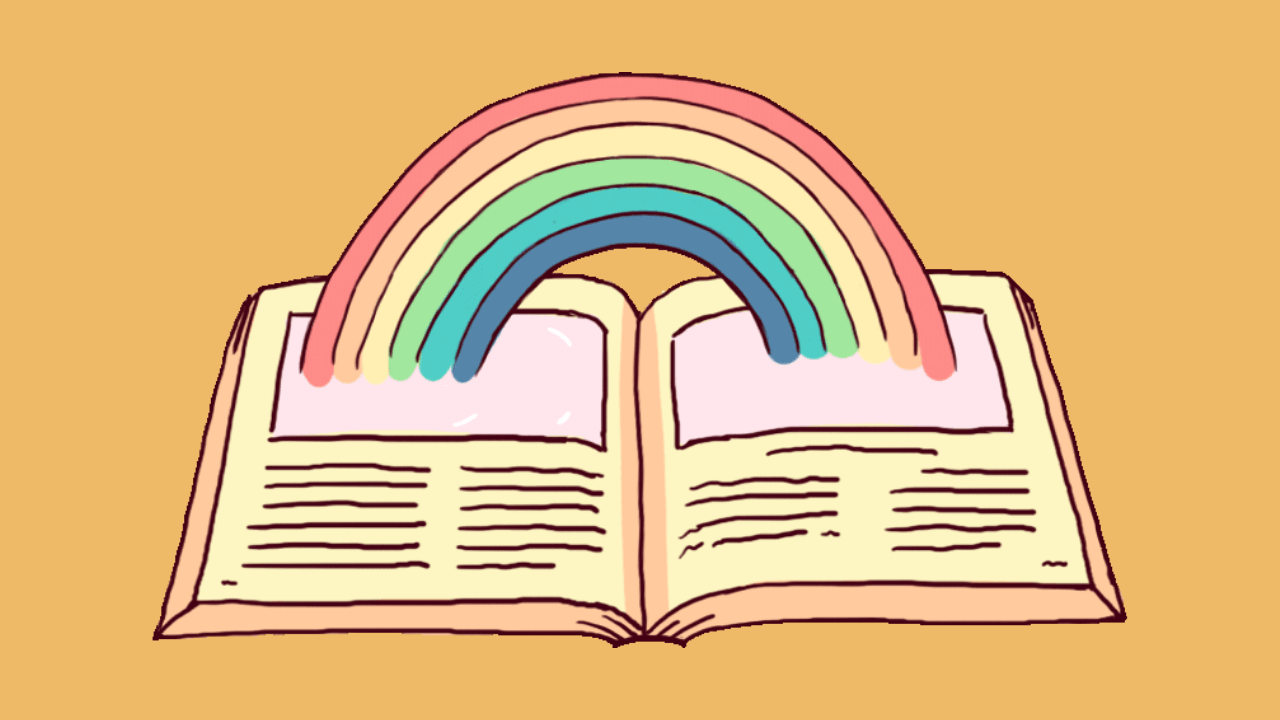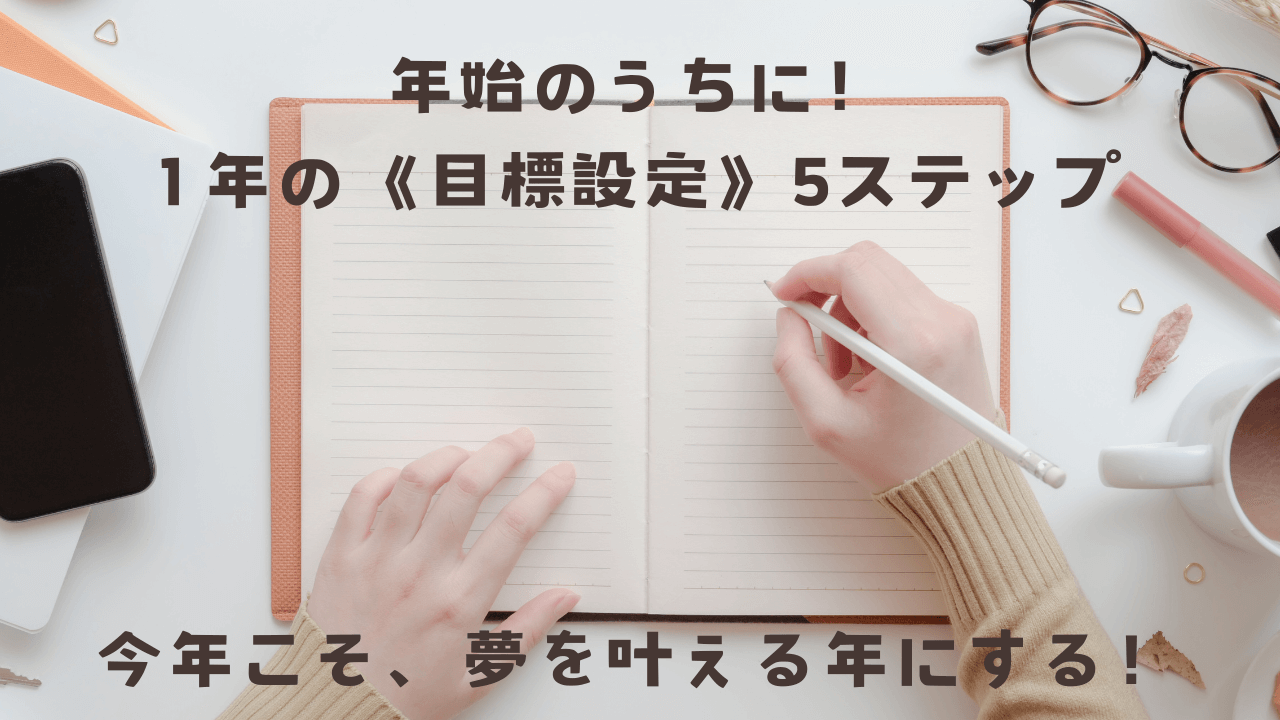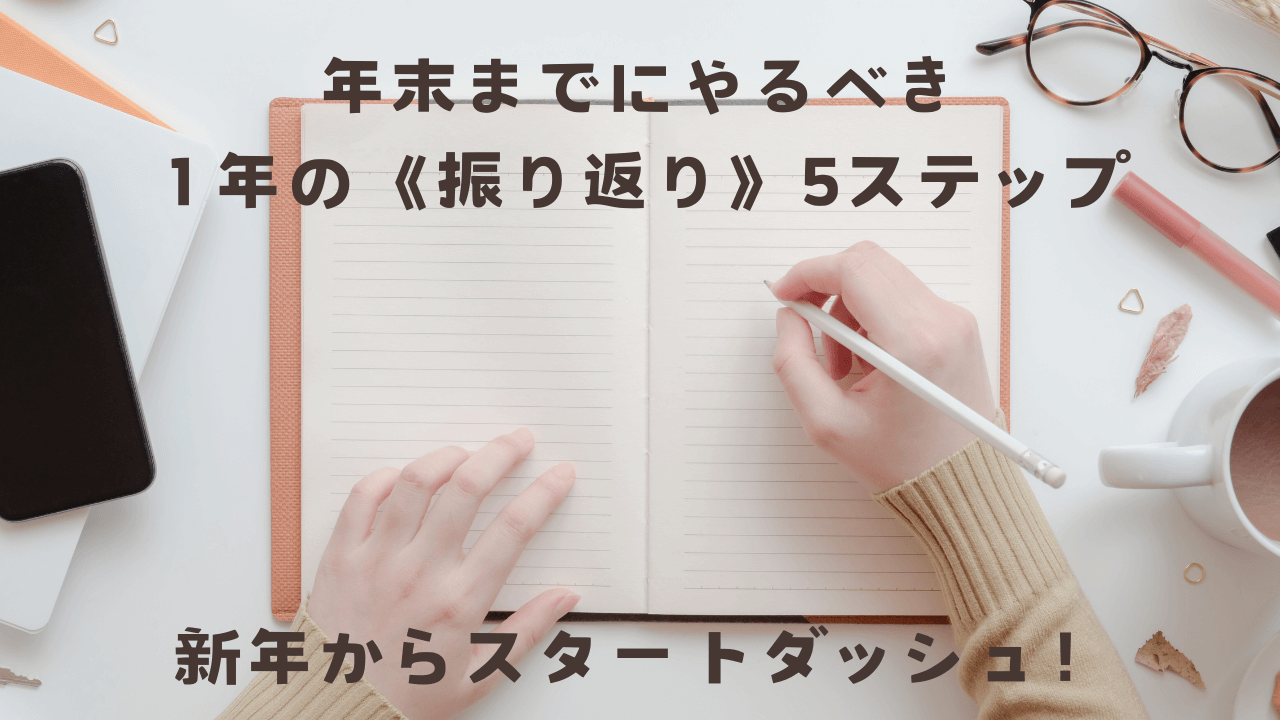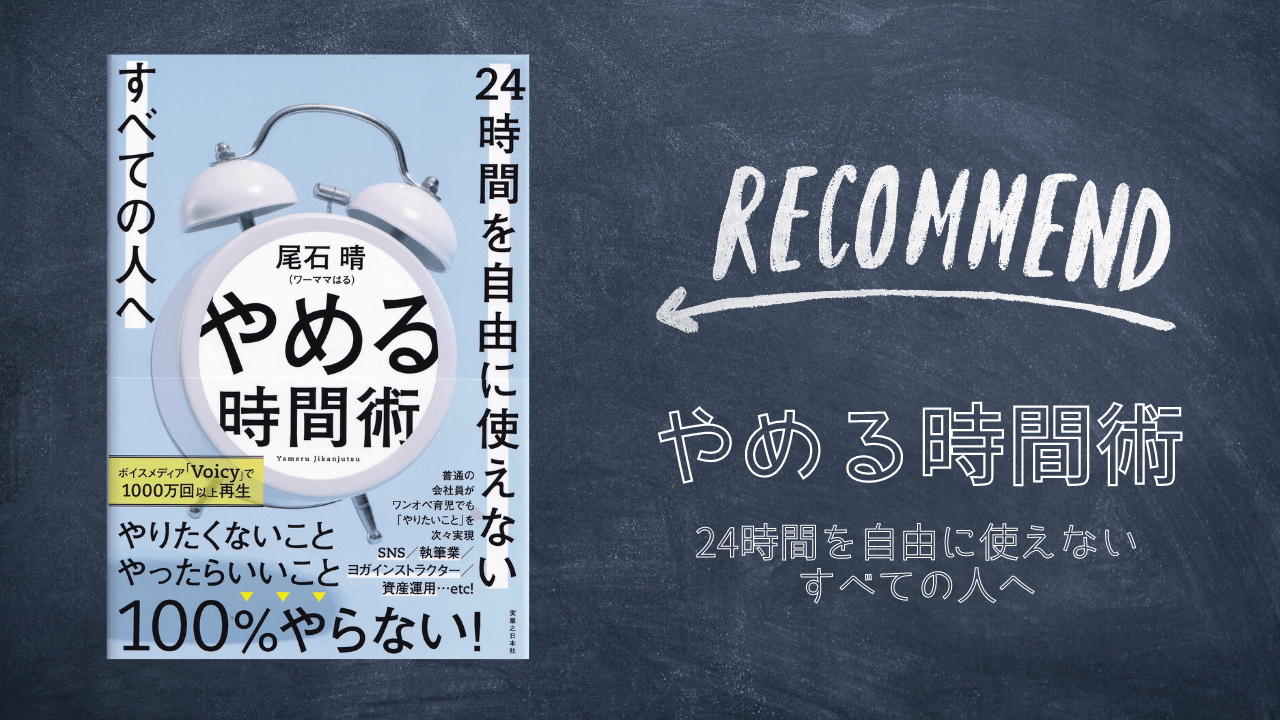「やらなきゃいけないこと」とか「ずっとやりたいと思ってること」って、なんでいつも後回しにしてしまいがちなんでしょう?
私はいつも自分がナマケモノであることを言い訳にしてしまうクセがあります・・・
でもそんな自分が嫌で、その現状を変えていくために副業や投資など色々なアクションを起こしてきました。
この記事では、私が「後回し」「先延ばし」「怠けグセ」を克服すべく日々やっていることを紹介します。
.png) とーこ
とーこ色んな文献を読み漁って実際にやってみた結果、超怠け者の私でも効果を感じられた順番に書いてあります。
秒でスタートするための作戦
①ベイビーステップ


ベイビーステップとは、赤ちゃんの最初の1歩レベルの「ちょこっと」程度のタスクに分解することを言います。
「毎日30分ジョギング」が目標なら・・・
- 「ウェアを出しておく」
- 「ウェアに着替える」
- 「靴を履く」
- 「とりあえず最初の1分は歩いてOKにする」
- 「次は1分だけ走ってみる」
などなど、これでもか! ってくらい最初の1歩を簡単にしておくのです。
毎日30分のジョギングは難しくても、(気持ち的な問題は置いといて、能力的に)ウェアに着替えられない人はいないですよね。
「これなら確実にできる」「1分でできる」「ひょっとしたら10秒でできる」と言えるくらいまで細かくしておくのがコツになります。
そして最初の1歩ができたら次の1歩、さらに次の1歩・・・というふうに、小さい1歩の積み重ねでゴールに近付いていくことができるのです。
10秒ならできる! と思わせてくれたのは『本気で変わりたい人の行動イノベーション』、
全ての行動は「仮」でいい! と行動の心理的ハードルを下げてくれたのは『「すぐ動ける人」の週1ノート術』です。
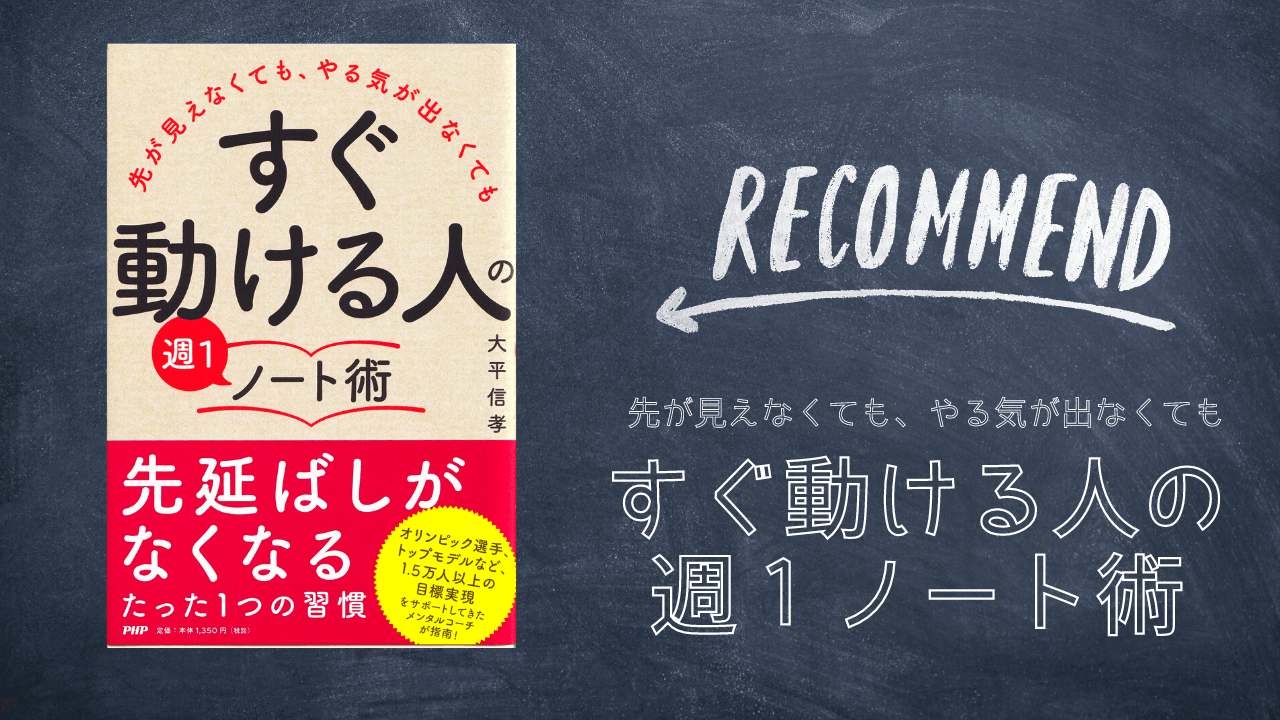
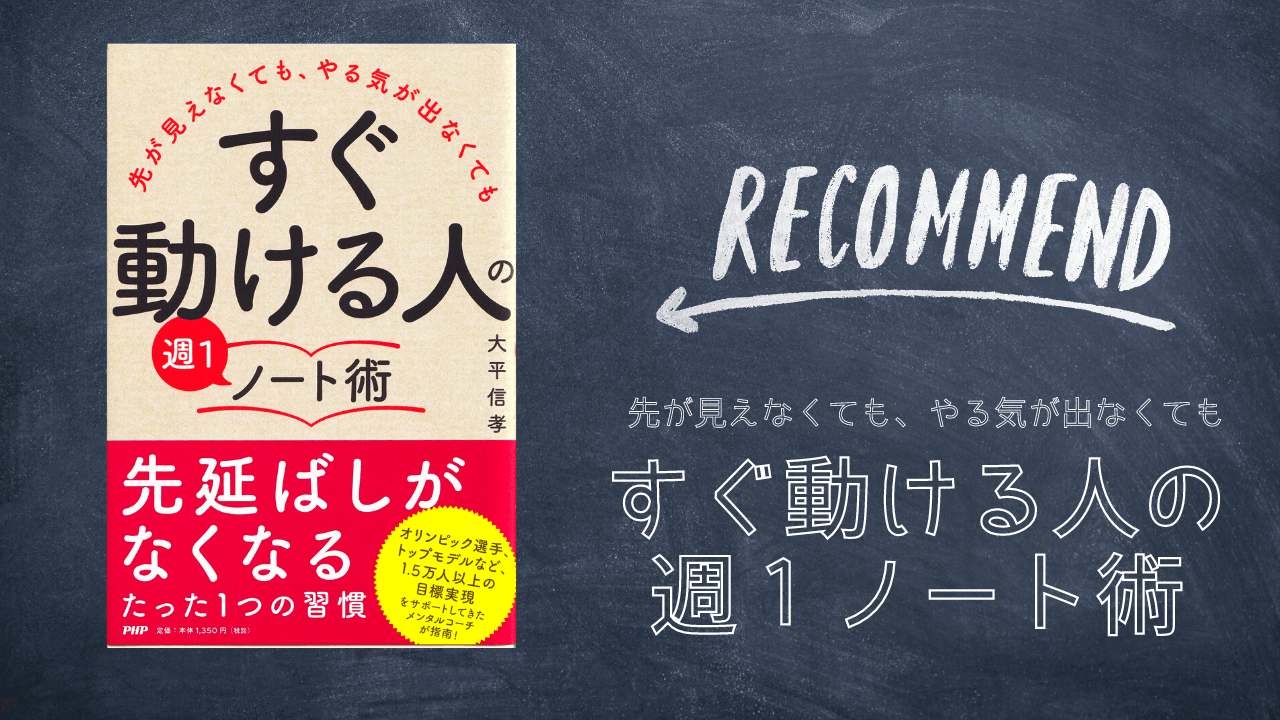
ただし、注意点が1つ。
締切があるタスクだと、細かく分解したタスクを1日1つ、とかのペースでこなしていては間に合わなくなってしまいます。
ベイビーステップにするとたしかに取り組みやすくはなりますが、締切とのバランスも同時に考えなくてはいけないのです。
ジョギングの例だと、半年後にマラソンの大会に出るのが目標だとしたら、3か月たっても毎日1分しか歩いてなかったら到底無理ですよね。
ベイビーステップ化はあくまでもスタートダッシュ。
一度行動を始めて乗ってきたようなら、次へ次へ、と進めていきましょう。
②「スイッチを入れる」場面を具体的にイメージする


イメージング的な手法になりますが、電気のスイッチをパチっとつけるように、頭の中で自分を起動する絵を思い浮かべています。
某塾のCMのやる気スイッチのように、自分の体にスイッチがついていて、それを押す瞬間をイメージするんです。
簡単なようで、意外と効果的。
集中に入るための儀式みたいな感じですね。
.png)
.png)
.png)
ポチッとな
③「スイッチを入れる」行動を作る
「スイッチを入れる」頭の中のイメージだけでは物足りない、いまいち気持ちを切り替えられないという場合は、実際にやる気をオンにできるような行動習慣を決めておきます。
これは「if then プランニング」と言われているもので、「〇〇をやったら●●をやる」という行動をパターン化して体に覚えさせるメソッドです。
例えば、
- ストップウォッチの計測開始を合図にする
- テンションの上がる曲を1曲だけ聴く(聴く曲はあらかじめ決めておく)
- 水を一杯飲む
- 1分瞑想する
- 1分ストレッチする
などを試してみてはいかがでしょう。
ただし、どこでもできて時間のかからない行動であることが大前提。
スイッチを入れるためだけの行動ですから、パッと切り替えになるようなアクションを選んで、ダラダラ続けてしまわないように気をつけてみてくださいね。
「if then プランニング」 について学んだのは、『複利で伸びる1つの習慣』と、
『やりぬく人の9つの習慣』です。
④ツールに凝らない


これは私がよくやりがちな反省から得た教訓なのですが・・・
テンションが上がる! やる気になれる! という口実で、専用のツールを用意するのはほとんど意味がなかったです。
これはそのデバイスがほしいがために理由を探しているに過ぎなくて、たぶん買ったところで行動が変わるかというと、そうはならないのが残念なところ。
ツールを検討する時間も余計にかかってしまいますしね。
今使っているものでなんとかできないか模索して模索して、どうしても「あのデバイスのあの機能が必須なんだ!」と具体的な必要性に迫られなければ、宝の持ち腐れになってしまいます。



何かを始める時「形から入る」のが多い人は身に覚えがあるのではないかと思います。気を付けて・・・!
また、ツールを縛ることで、そのタスクをやるシチュエーションが限られてしまわないかも注意が必要です。
重いので持ち歩きが苦痛で家じゃないとできなくなってしまった、とかですね。
ツールはいきなり新調しない!
今家にあるものでひとまずなんとかしてみる!
これを徹底した方が、早くスタートしやすくなりますよ。
⑤スキマ時間でやることを決めておく


スキマ時間ができたらコレをやる、と決めておくと、いざスキマ時間ができた時に「何をやろうか」と悩む時間を節約できます。
ついでに、経験上、タスクは3個程度にとどめておくことをオススメします。
なぜなら、タスクが多いとそれだけで「何をやろうか」迷ってしまい、決めておく意味がなくなってしまうから。
例えば次のように、シチュエーションで絞っておくと便利です。
- 5分以内:SNSチェック
- 5〜15分以内:資格試験の問題を解く
- 15分以上:仮眠、または掃除1箇所
- 家:ストレッチ
- 通勤途中:ニュースチェック
- そのほか外出先:本を読む
集中するための作戦
①今日の・今週の「PICK1」を決めておく


『PICK THREE 完璧なアンバランスのすすめ』の本が参考になりました。
要約すると、「人生の今の期間に比重をおくことを3つに絞るべき」というものです。
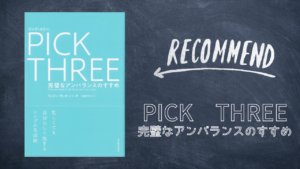
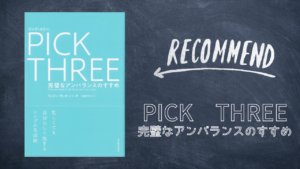
当面「仕事・家族・友人」に比重を置くと決めたら、そのほかのこと、例えば「運動」に関することは後回しにしてOK、としてしまいます。
価値観や役割に優先順位をつけるイメージですね。
でも、しばらく経ったらまた新しく3つの重点項目を決めて、人生全体でバランスが取れれば良いよね、とゆるく折り合いをつけていく考え方です。
この本では数ヶ月〜数年単位のスパンでこの「PICK3」を決めている事例が多くなっていますが、私はその中でも優先度を決めて最重要の「PICK1」を決めています。
今日は○○集中DAY、今週は○○週間、など自分の標語を決めてプロジェクトにすると、自分にとっての優先度がより浮き彫りになり、集中して取り組みやすくなるのでおすすめです。
.png)
.png)
.png)
忙しい日も、「PICK1」に関することを少しでもできたら前進できてる! と思えるよ
②「計画」時間と「行動」時間を完全に切り分ける


私は手帳が大好きだからか、行動の最中に次の計画を考えてしまう、というのをやりがちです。
ですがそのたびに行動が止まり、集中が切れる状態になってるんですよね。
PDCAサイクルでいうなら、「D(Do)」と「C(Check)→A(Action)→P(Plan)」をいかに分離させるか、が大事だと感じています。
私の場合、ざっくり曜日で分けてしまうのが生活スタイルに合っていました。
月曜日から金曜日が 「D(Do)」 、土曜日が「 D(Do) の予備日」、日曜日が 「C(Check)→A(Action)→P(Plan)」 のような分け方です。
これにより、「平日はとにかく計画したことをやる! このままでいいのかな・・・とかは一切考えない!」と、1週間単位では方向性を大きく変えずに突っ走ることになります。
そして週末に「1週間の振り返りをして、改善点を来週の計画に入れよう」という流れができあがります。
.png)
.png)
.png)
平日は「Do」に集中するための心構え。
次に短期的な作戦です。
「平日はD(Do)」と決めていても、やってる最中にモヤモヤと感じることや、やらなきゃいけないことをふと思いだすことが出てきます。
そんな時は「書き殴れるノート」を1冊用意しておいて、そこにメモしておく。
メモしたらそのことは忘れて、元のやるべきことに戻るようにしています。
手帳を使っている人でも、「考え事をなんでもいくらでも吐き出せる場所」としてノートを併用するのはオススメです。
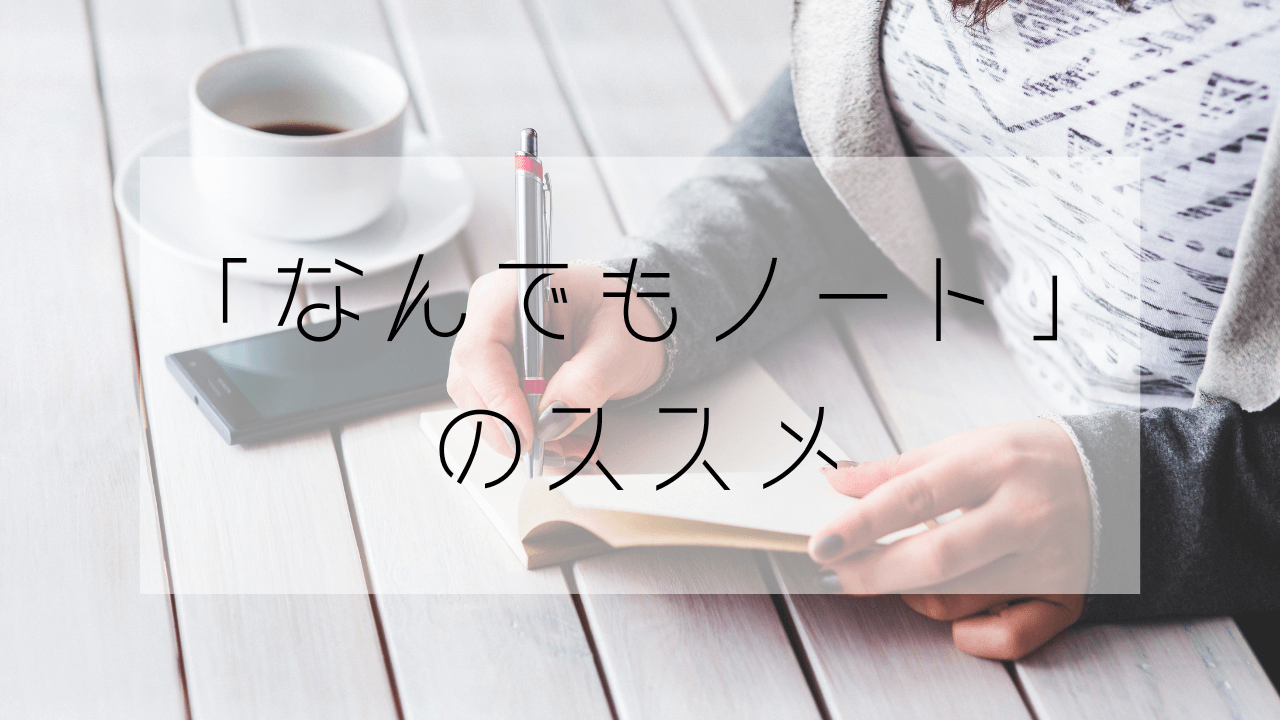
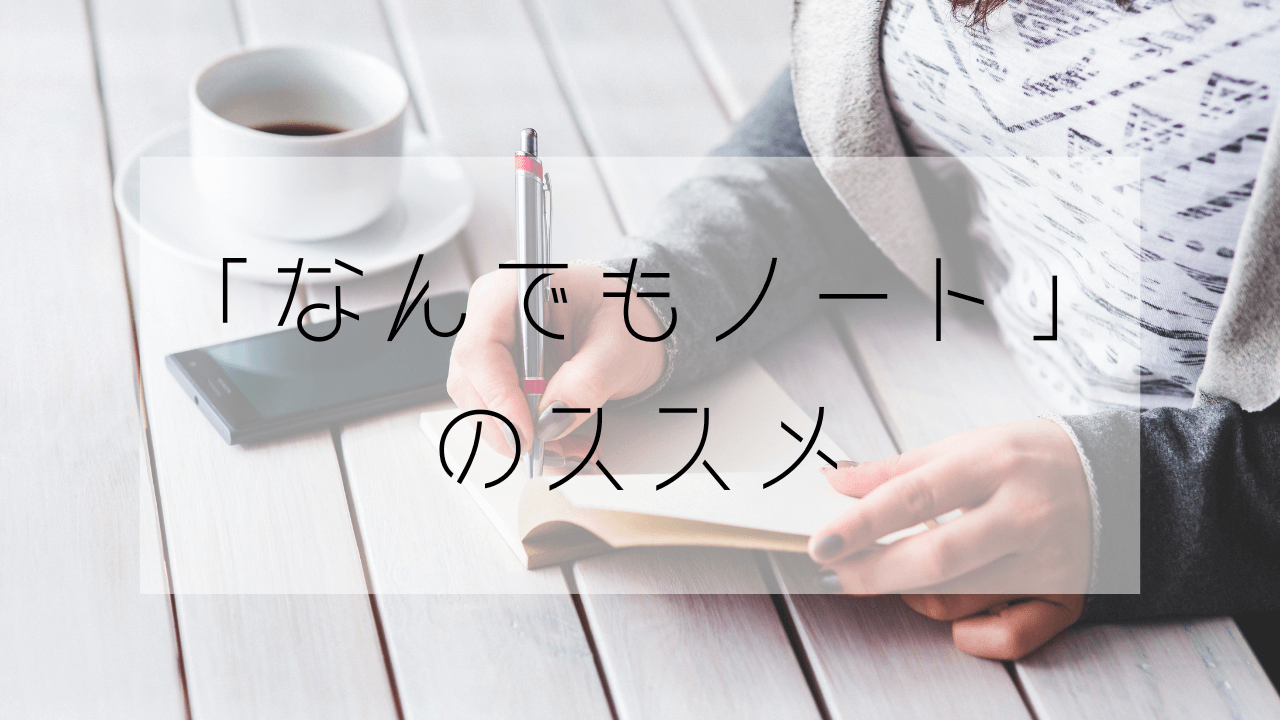
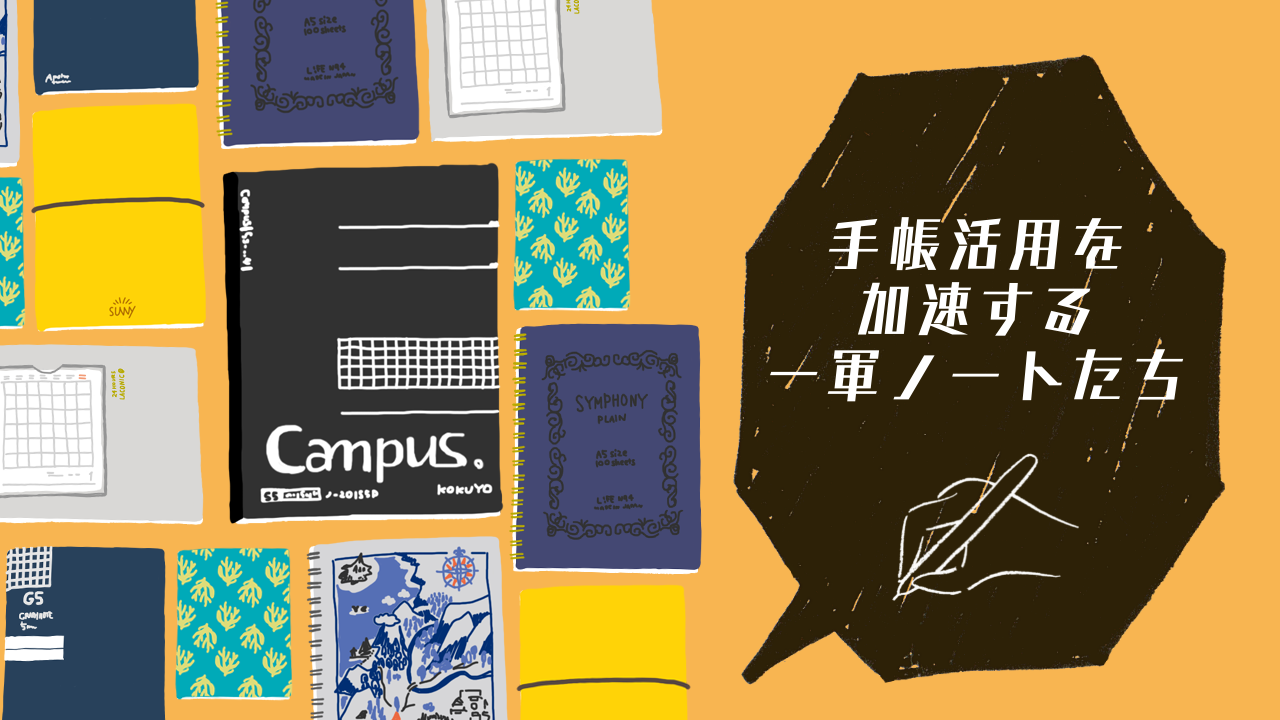
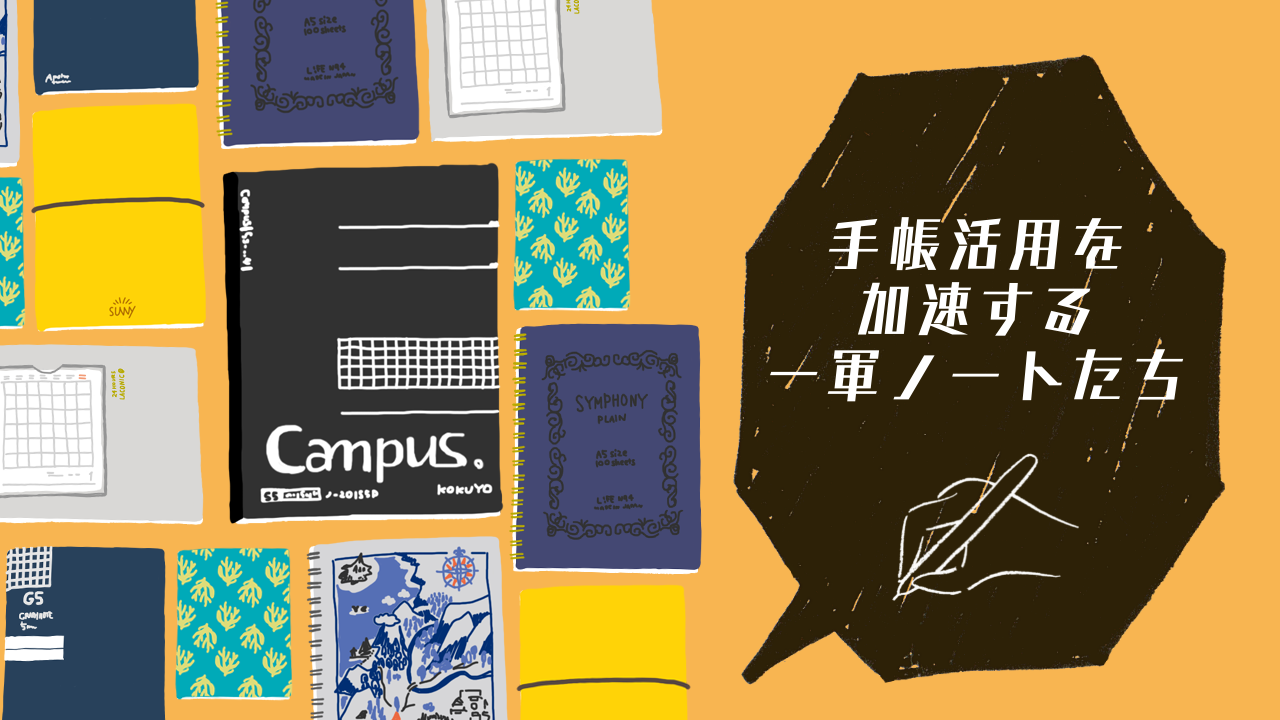
「今ここ」に集中する心のあり方は、マインドフルネスやアドラー心理学で提唱されています。
③「何」に集中し、「なぜ」を考えない
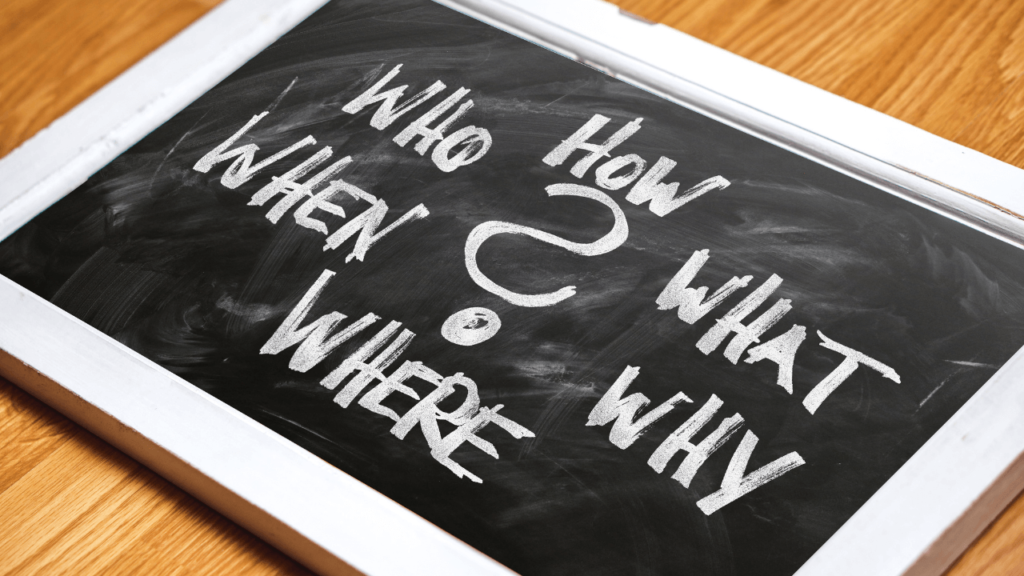
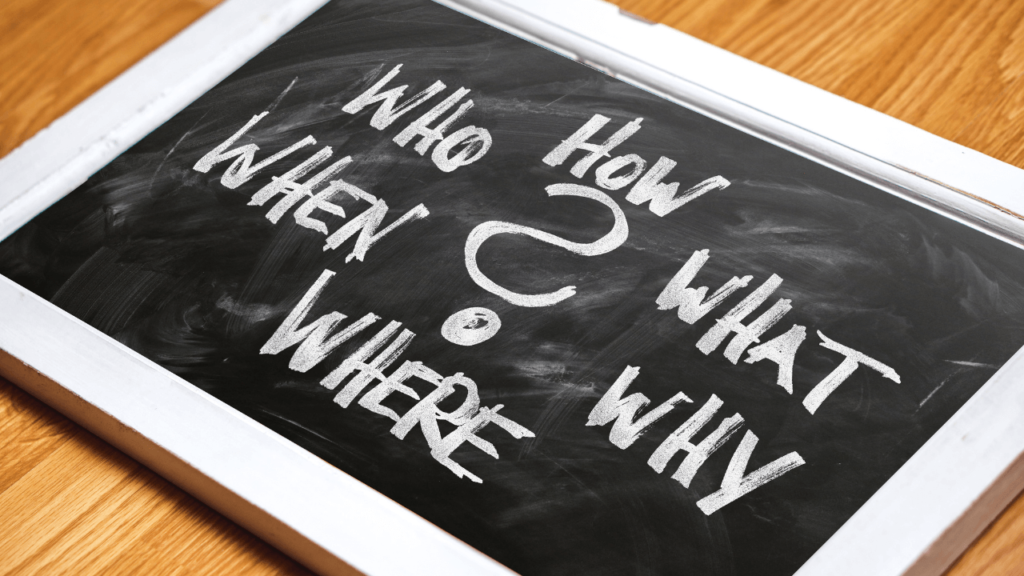
何かをやっているあいだはそのタスクのみに集中すべきですが、そのタスクに関することでも雑念が入ることはありますよね。
「こんなことしていて意味があるのだろうか・・・」「本当に成果が出るのだろうか・・・」というような感じで、特に初めてのことをやっている時ほど、不安で手が止まってしまうことが多いように思います。
ですが 「意味があるかないか」を振り返るのはアクションが終わってからでも遅くありません。
中途半端になってしまうと、続けるかやめるか、その判断材料となる経験も不足した状態で決断しないといけなくなるので、間違った方向に進んでしまうことも考えられます。
やってみないと次の景色は見えてこないですし、むしろ行動しないと出るはずの成果もゼロ。
一度計画したのなら、一区切りがつくまでは突っ走るべきです。
④デジタルデトックス


現代人にとってデジタルデバイスはなくてはならないツール。
便利な反面、SNSの通知やゲームアプリの誘惑に耐え、目の前のことに集中し続けるのがどんどん難しくなっています。
.png)
.png)
.png)
「うっかり」「つい」「反射で」スマホに手を伸ばした5秒がいつの間にか1時間経過・・・なんてあるあるです



そしていつも後悔するんだ・・・
だからこそ、デジタルツールと適度な距離を取るための対策をしておく必要があるんです。
一番手っ取り早いのは「物理的に距離を置く」という方法。
作業場所とは別の部屋に置いたり、一定時間パートナーに預かってもらったり、とにかく簡単には触れなくします。
あとはスマホを見ない時間に応じて育つアプリを使ったり、逆に起動して放置していないと進まないアプリも、他の画面を見なくなるという意味では有効でした。
私みたいに誘惑に負けやすい人は、とにかくいかに見ないか・触らないかを考えないと負け続きになってしまいます。
時計代わりに使わない、タイマーはキッチンタイマーを使う、といったように、状況が許すなら多少面倒でも別のツールを使うように気をつけましょう。
参考にしたのは『時間術大全』。
デジタルデトックスに限らず、やるべきことに集中するための作戦が挙げられた本です。
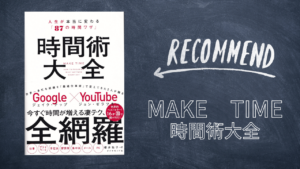
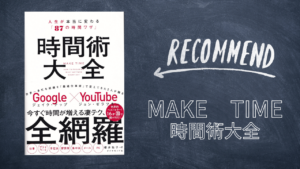
⑤最適な室温・湿度を保つ


部屋が最適な環境になっていないと集中どころの問題じゃないので、室温や湿度も地味ですが大事な準備。
気持ちのいい環境で過ごすと、暮らしと気持ちに余裕もできますし、電気代はそのための投資としても法外にお金がかかるわけじゃないですよね。
電気代を年間数千円ケチるくらいなら、気持ちよく暮らした方が絶対お得ですよ!
.png)
.png)
.png)
こたつでぬくぬくすると怠けてしまう人は、エアコンで部屋全体の暖めから!
まとめ
秒でスタートするための作戦
- ベイビーステップ
- 「スイッチを入れる」場面を具体的にイメージする
- 「スイッチを入れる」行動を作る
- ツールに凝らない
- スキマ時間でやることを決めておく
集中するための作戦
- 今日の・今週の「PICK1」を決めておく
- 「計画」時間と「行動」時間を完全に切り分ける
- 「何」に集中し、「なぜ」を考えない
- デジタルデトックス
- 最適な室温・湿度を保つ
.png)
.png)
.png)
超ナマケモノの自分を「行動させる」ためのポイントについて私の経験をもとに紹介しました。
.png)
.png)
.png)
自分のツボを見つけられると、グッと行動しやすくなります。
色々試してみてください!